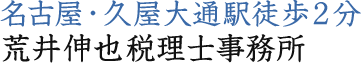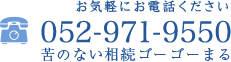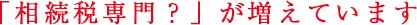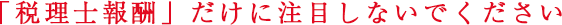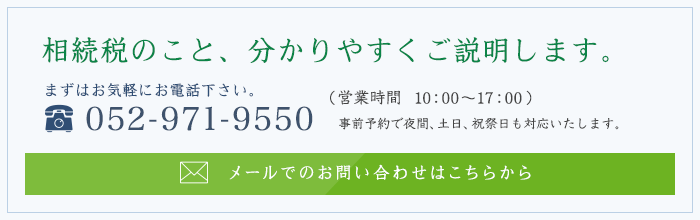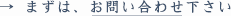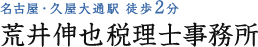相続税申告書の作成

個々の相続財産の確認を行い、現存する預貯金・不動産等に加えて、例えば預金通帳の入出金から、、、家族契約の保険料の支払い、過去に購入した資産、過去に行った贈与、、、等を把握して検討させていただいて、相続財産の申告漏れを防ぎます。
相続税評価額の算定については、財産評価基本通達により土地、有価証券等の評価額の算定を適正に行い、特に路線価地域の土地については必要に応じて現地調査を実施して減額要因の把握に努め、適正に評価いたします。
遺産分割協議が円満に円滑に進むように、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、各種の税額控除等の説明を行い、いろいろな遺産分けのパターンでの相続税の試算、二次相続についても検討してアドバイスをいたします。
無用な税務調査を回避するため、相続税申告書には必要に応じて税理士法33条の2の添付書面制度を利用したり、入出金検討表や事実関係の説明書を添付しております。
常に節税と適正な申告を念頭にして、相続税の申告業務を行っております。

当事務所は、円満な相続が第一と考えています。
節税はその次です。
相続税を安くしたい、節税したいと考えるのは当たり前ですが、その結果親族間で争いが起これば取り返しがつきません。家庭裁判所の扱う遺産分割事件のうち相続遺産価格5,000万円以下の争いが全体の75%を占めています。名古屋市内に自宅を所有し老後のための預金2,000万円あればおおよそ5,000万円です。一般的な家庭での遺産争いが3/4を占めているわけです。
子供同士の仲が悪い、再婚していて前妻との間に子がいる、妻と長男の仲が悪い、、、、遺産争いが心配なら、早めに遺言書を作成しておく必要があります。法的に誤りのない遺言書を作成し遺言執行人を指定しておくと、遺産分割協議を行うことなく財産承継ができます。
特に子のいない夫婦の場合は、必ずお互いのために遺言書を作成してください。子のいない夫婦で夫が死亡した場合、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪が相続人になります。遺言書がない場合、妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行い、話がまとまらないと自宅の名義変更等ができません。不安な状態が続きます。夫が生前に遺言書を作成して「全財産を妻に相続させる。」と書いておけば、遺産分割協議は不要です。兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺産分割協議をしなくても「全財産」を妻が相続できます。
いわゆる「おひとりさま」も、遺言書を作成しておくと、お世話になった人に遺産を引き継げます。
遺言には、自分で作成する自筆証書遺言もありますが、法律の専門家の公証人が関わる公正証書遺言がおすすめです。公証人が関与しますから無効になることはありませんし、確実に保管してもらえます。
円満な相続のため、、、
遺留分に配慮した公正証書遺言の作成をサポートしております。

例えば被相続人の相続財産が、自宅の土地建物評価額3,000万円、 預貯金 1,000万円、とします。
相続人は長男(自宅に同居していた)、次男(別居)の2人です。法定相続分は長男1/2,次男1/2で、取り分は2,000万円ずつです。長男は「自分が自宅を相続し、次男には預金を相続させたい」、次男は住宅ローンをかかえていて「法定相続分での遺産分け」を希望しています。 分割協議がまとまりません。
生前に被相続人が「長男に自宅を相続させる。預金は次男に相続させる。」との遺言書を書いていれば、次男の遺留分は害されていませんから、遺言書通りの遺産分けができます。また、被相続人が生前に長男を受取人にした1,000万円の生命保険に入っていれば、長男は保険金1,000万円を自宅を相続する代償金として次男へ支払うことができ、その結果、法定相続分とおりの遺産分けができます。
長男: 自宅 3,000万 - 代償金1,000万円 = 2,000万円
次男: 預貯金1,000万 + 代償金 1,000万円 = 2,000万円
一次相続のみならず、次の二次相続を考えたトータルで節税を考えて、アドバイスいたします。
円満な相続のための
遺産分けのアドバイスいたします

申告額が過少であると想定される場合や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される場合には、必要に応じて実地調査が行われます。
通常は初日に税務署員が納税者宅に出向いて事実関係の確認や申告書作成の基礎資料の確認をおこない、その後は金融機関等で調査が行われます。
令和5事務年度の実績では実地調査の行われた事案の84.2%で申告漏れが指摘され、1件当たりの申告漏れ課税価格は3,208万円、追徴税額は859万円でした。
実地調査は終了までに数か月を要することもあり、調査を受ける納税者の心的負担は大きく、できれば避けて通りたいものです。
当事務所は常に申告に当たっては税務調査で問題となりうる事項を検討整理して、節税と適正申告をモットーに申告いたします。
また、必要に応じて書面添付制度を利用しております。

節税対策は早期に計画的に行うことが必要です。
早期の対策は節税効果が期待できます。
相続後の節税対策は、きわめて限られています。
イ、生前贈与
暦年課税の贈与で毎年現金を子や孫へ贈与することが、最も確実な節税方法です。贈与税の基礎控除額は110万円ですから、1年間の贈与額がこれ以下なら贈与税はかかりません。子供2人・孫2人の合計4人に5年間にわたって110万円づつ贈与すると2,200万円を無税で財産移転できます。もっと早く財産移転したいなら贈与金額を200万円にします。すると基礎控除額を越える90万円の10%、9万円の贈与税がかかります。5年間で4,000万円の財産を贈与税180万円で次の世代に移転できます。
被相続人から相続開始前7年以内に贈与がされた場合には、それらの贈与財産は相続財産に加算されますから、加算されないように早い時期からの贈与がお勧めです。
注意したいことは、贈与した現金は受贈者が日常的に使用している銀行口座に振り込むことです。 そして受贈者が自由に使える状態にしておくことです。現金での授受は避けてください。 贈与の方法を誤ると税務調査で、「名義預金」と認定されて、相続財産に全額取り込まれることにもなります。
暦年課税の贈与は、確実な節税対策です
ロ、贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年を越える夫婦の間で「居住用財産」「居住用財産の購入資金」 の贈与があった場合、2,000万円の控除が適用できます。つまり夫が所有する自宅の土地建物を評価して2,000万円以下であれば、妻に贈与してもこの配偶者控除で贈与税はかかりません。自宅の土地建物の評価が3,000万円なら、2,000万円を控除した1,000万円が贈与税の課税対象になります。
この配偶者控除は、贈与が相続開始前3年以内におこなわれていても、相続財産へ加算されません。
贈与税の配偶者控除、非課税特例、、、
節税対策に活用できます
ハ、生命保険金の活用
保険料負担者・被保険者が被相続人の場合、相続人が死亡保険金を取得すると、非課税とされる部分があります。
非課税金額=500万円 × 法定相続人の数
4人家族で父親が死亡した場合、相続人は3人ですから1,500万円までの死亡保険金は課税されません。 2,000万円の死亡保険金なら、非課税の1,500万円を控除した500万円が課税対象になります。
この死亡保険金の非課税は、節税対策になります。もし、まだ死亡保険金の非課税枠が残っているなら、限度額まで使ってください。一時払いの死亡保険を活用することで、預貯金を死亡保険金として相続するだけで節税できます。
生命保険の非課税枠を限度額まで使っている場合でも、節税に活用できる保険商品ははあります。 お気軽にご相談ください。
生命保険を活用した節税対策もご相談ください、

相続税の申告書を提出していても、計算誤りがあり税金が減る場合は法定申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」という減額請求ができます。
「申告書は提出したが、土地の評価が高すぎた気がする」とお考えなら、当事務所がセカンドオピニオンとして、土地評価の再検討をいたします。そして払いすぎの税金があれば、還付請求いたします。
他の税金に比べて相続税の税額は大きくなりますから、ひとりの税理士の判断にすべてを任せることはリスクがあります。
払いすぎの相続税、還付請求いたします。

生前のうちに不要な財産を処分して、相続人の負担を減らしておくことは、円滑な相続には必要です。
特に不要な土地は生前に処分し、遺産分割のしやすい預貯金に変形させておくことは大切です。老朽化した低収益の貸家、権利関係の複雑な土地は負の遺産にもなりかねません。
相当額の相続税が見込まれていて、それに見合う預貯金が不足する場合、生前に不動産を処分して納税資金の手当てをしておくことが必要です。あるいは相続後の売却のための何らかの準備をしておく必要があります。
介護施設への入居・利便性の良い賃貸物件への転居予定があり、自宅を売却することもあります。自宅を売却すると居住用財産の譲渡特例が適用できます。譲渡益が3,000万円までは特別控除が適用できます。例えば自宅を3,000万円で売却すると、この特例で税金がかからずに手元に3,000万円がそのまま残ります。相続後に相続人がその自宅を売却しても、要件不備でこれらの特例が適用できないことがあります。
土地譲渡には各種の課税特例があり、税額も多額になるため事前の検討が必要です。不動産の有効活用、不動産の売却等をお考えの方には、提携不動産会社等のご紹介もしております。
不動産の譲渡、交換についても、
お気軽にご相談ください

社会貢献への関心が高まり、寄付や遺贈への感心が高まっています。
公益法人の側もパンフレット等で寄付、遺贈による寄付をアピールしています。公益法人等へ不動産を生前に寄付する場合、あるいは遺言で土地を遺贈する場、寄付した人に譲渡所得税が課税されます。
少し難しい話ですがその不動産を時価で譲渡したと見なして課税されますから、税額は多額になります。しかし一定の公益法人への寄付・遺贈は、一定の要件に該当していれば、申請をすることで非課税となり課税されません。この申請手続きは、要件が細かく極めて専門的です。
公益法人へ寄付申請(措置法30条)、
サポートいたします